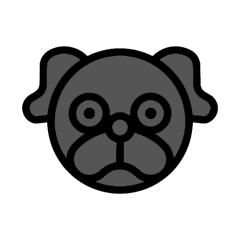マツダカコ最新长篇大作《女王達の学舎》(4月3日更新鞭打 小便 舔阴)
添加标签
黒椿学園。
そこは次世代を背負って立つ女性リーダーを育成する為に作られた中高一貫の私立学校。
そこに入学した令嬢達は中等部の三年間で支配者としての振る舞い、奴隷の扱い方を学ぶ。
そして高等部ではいよいよ実際の「オス奴隷」を飼育調教し、自分より『下』の者の扱い方を本格的に学ぶ。
奴隷として扱われるとは知らずに、「男子生徒」として募集されて入学した15歳の少年達は、自分と同い年の女生徒に飼育され、奴隷へと堕とされていく....
そこは次世代を背負って立つ女性リーダーを育成する為に作られた中高一貫の私立学校。
そこに入学した令嬢達は中等部の三年間で支配者としての振る舞い、奴隷の扱い方を学ぶ。
そして高等部ではいよいよ実際の「オス奴隷」を飼育調教し、自分より『下』の者の扱い方を本格的に学ぶ。
奴隷として扱われるとは知らずに、「男子生徒」として募集されて入学した15歳の少年達は、自分と同い年の女生徒に飼育され、奴隷へと堕とされていく....
作者地址:https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=14775447
黒椿(クロツバキ)学園。
そこは中高一貫教育を行なっている国内屈指の超名門女子校で、何人もの女性経営者や女性政治家を輩出している。その名を知らぬ者はない。
パンフレットやホームページには卒業生たちの華々しい活躍、そして在校生の名門大学への進学実績や、インターハイを総なめするような部活動の戦績が所狭しと記載されている。
しかし、そんな黒椿学園の豪華絢爛なホームページの隅には「男子学生募集中」の小さな文字。
そこをクリックすると
「高等部からのみ募集中。学力試験無し。学費無料。全寮制。就職率100%」
と書かれている。
この破格とも言える条件に、公立高校の受験を全て失敗した中学3年生、山吹俊太(ヤマブキシュンタ)は飛びついた。
「お母さん、ここなら俺も高校に入れる!」
「あら、学費無料、全寮制……?」
シュンタの家は決して裕福ではなかったので、両親もその条件に喜び、出願した。
そして、4月。
巨大かつ豪華絢爛な大講堂で行われた入学式を終え、入学生の保護者たちがそれぞれの帰路についた後、入学した男子生徒たちは告げられた各々のクラスへと向かった。
クラスはAからGの7クラス。シュンタのクラスは1-Aで、男子が20名、女子が20名だった。
各クラス40名×7クラスで一学年は280名。
そして男子と女子はそれぞれ140名で、ちょうど半々となるようにされていた。
(す、すごい……体育館も凄かったけど、校舎もすごいぞ!)
歩いている途中、シュンタはついキョロキョロと建物を見渡してしまった。
廊下には赤い絨毯が敷いてあり、天井には高級ホテルでしか見ないようなシャンデリアが吊り下がっている。
学校というよりも、貴族が生活するような屋敷をイメージしてしまうほどに黒椿学園は立派で豪華だった。
(僕は、こんなところで生活できるのか……)
シュンタは目を輝かせた。そう、黒椿学園は全寮制。つまり、この学園のどこかにすでにシュンタの部屋があるのだ。
(どんな豪華な部屋なんだろう。2人1組の相部屋だと聞いてるけど、ルームメイトはどんな人なんだろう……あれ?)
シュンタはふと、妙なことに気がついた。
(女子生徒は、もう制服なんだ……)
自分も含め男子は全員私服を着ている。入学時の説明事項には「入学後に制服を与える」と書いてあった。しかし、女子は既に制服を着ている。
(女子は中学からだから、高等部でも同じ制服なのかな?)
シュンタは深く考える事もなく、適当に自己解決して教室への歩みを進めた。
そして、教室。1-Aと書かれたプレートが付いている。
(ここで、僕の青春が始まるんだ! 部活に入って、彼女も作って……楽しく3年間過ごすぞ!)
シュンタが決意を固めて教室に入ると、教室の中もさらに美しかった。綺麗に板張りされたフローリングの床。並んでいる生徒用の机は通常のものよりも少し大きく、椅子はまるでソファのようなクッションが付いていて座りやすそうな素材が使われている。
机は綺麗に20席並んでおり、正面には教壇と黒板。天井には宝石のような照明。窓の外には美しい庭園の景色が見える。
(あれ、20席……?)
シュンタは気がついた。1クラス40人いるはずなのに、席は縦に4席並んだ列が5列。何度数えても20席しかない。
「な、なんで……?」
シュンタだけでなく他の男子生徒も気づいたらしく、不思議そうな顔を浮かべていた。
そして、そんな私服の男子生徒たちをよそに、黒を基調とした中に美しく赤や金のラインが入ったブレザーとスカートの制服に身を包んだ女子生徒たちはそれらの豪華な席に次々と座っていった。
女子たちは男子と目を合わせることも口を訊くこともないうちに全員が席についた。教室の中は、落ち着いて席についている女子生徒と不安そうな顔を浮かべながら立っている男子生徒というようにくっきりと分かれた。
「はいみんな、進学おめでとう」
そうしていると、教師と思われる女性が教室に入ってきた。手には何かが入った段ボール箱を持っている。
「私の自己紹介は要らないね。高等部からもよろしく。じゃあ早速始めましょう。道具を配るからね」
その女教師も男子生徒に対しては一言も話さず、箱の中身を女子生徒に配り始めた。
女子に配られているものを見ると、それは鎖と首輪、短い乗馬鞭、南京錠とその鍵。そしてもう一つはシュンタには何なのか分からない器具だった。
(なんだあれ、鉄の筒?何に使うんだ?)
「はい、道具は行き渡ったね。じゃあみんな、自分の奴隷を席の隣に連れてきて」
「へ?」
教師の言葉と共に、女生徒たちは立ち上がって男子生徒に近づき、手や髪を掴んで自分の席の近くへと連れていった。
「ほら、早く来なさい」
シュンタの前にも、一人の女子が来てシュンタの服を掴んだ。
その女子はクラスの中で誰よりも美しかった。
背中まで伸びたブラウンの髪、透けるように白い肌。くっきりと通った鼻筋、大きな目。そして
彼女は、シュンタが今まで見た女性の中で最も美しいと思える容姿をしていた。
(……あれ?)
シュンタは一つ疑問に思った。教師は「奴隷を自分の席の近くに」と耳を疑うようなことを言った。そして、女子たちは男子を掴んで自分の席の近くへと連れて行った。
つまり、
「僕達は、奴隷……?」
「フッ!」
シュンタの小さな呟きに、シュンタの服を引いて歩く女子生徒は鼻で笑った。
「そっか、まだ知らされてないんだっけ? あなたたちは」
「え……」
シュンタの心臓がドクンと一度大きく跳ね、一筋の冷や汗が頬を伝った。
「そうよ、あなたたちオスはこの3年間、私たちの奴隷。そして」
その女子生徒は自分の席に座り、顔の前にかかった髪を手で後ろに弾き、長い脚を組んで、言った。
「あなたは3年間、私専用の奴隷よ。二度と普通の生活ができなくなるほど調教してあげるから覚悟しなさい」
黒椿(クロツバキ)学園。
そこは中高一貫教育を行なっている国内屈指の超名門女子校で、何人もの女性経営者や女性政治家を輩出している。その名を知らぬ者はない。
パンフレットやホームページには卒業生たちの華々しい活躍、そして在校生の名門大学への進学実績や、インターハイを総なめするような部活動の戦績が所狭しと記載されている。
しかし、そんな黒椿学園の豪華絢爛なホームページの隅には「男子学生募集中」の小さな文字。
そこをクリックすると
「高等部からのみ募集中。学力試験無し。学費無料。全寮制。就職率100%」
と書かれている。
この破格とも言える条件に、公立高校の受験を全て失敗した中学3年生、山吹俊太(ヤマブキシュンタ)は飛びついた。
「お母さん、ここなら俺も高校に入れる!」
「あら、学費無料、全寮制……?」
シュンタの家は決して裕福ではなかったので、両親もその条件に喜び、出願した。
そして、4月。
巨大かつ豪華絢爛な大講堂で行われた入学式を終え、入学生の保護者たちがそれぞれの帰路についた後、入学した男子生徒たちは告げられた各々のクラスへと向かった。
クラスはAからGの7クラス。シュンタのクラスは1-Aで、男子が20名、女子が20名だった。
各クラス40名×7クラスで一学年は280名。
そして男子と女子はそれぞれ140名で、ちょうど半々となるようにされていた。
(す、すごい……体育館も凄かったけど、校舎もすごいぞ!)
歩いている途中、シュンタはついキョロキョロと建物を見渡してしまった。
廊下には赤い絨毯が敷いてあり、天井には高級ホテルでしか見ないようなシャンデリアが吊り下がっている。
学校というよりも、貴族が生活するような屋敷をイメージしてしまうほどに黒椿学園は立派で豪華だった。
(僕は、こんなところで生活できるのか……)
シュンタは目を輝かせた。そう、黒椿学園は全寮制。つまり、この学園のどこかにすでにシュンタの部屋があるのだ。
(どんな豪華な部屋なんだろう。2人1組の相部屋だと聞いてるけど、ルームメイトはどんな人なんだろう……あれ?)
シュンタはふと、妙なことに気がついた。
(女子生徒は、もう制服なんだ……)
自分も含め男子は全員私服を着ている。入学時の説明事項には「入学後に制服を与える」と書いてあった。しかし、女子は既に制服を着ている。
(女子は中学からだから、高等部でも同じ制服なのかな?)
シュンタは深く考える事もなく、適当に自己解決して教室への歩みを進めた。
そして、教室。1-Aと書かれたプレートが付いている。
(ここで、僕の青春が始まるんだ! 部活に入って、彼女も作って……楽しく3年間過ごすぞ!)
シュンタが決意を固めて教室に入ると、教室の中もさらに美しかった。綺麗に板張りされたフローリングの床。並んでいる生徒用の机は通常のものよりも少し大きく、椅子はまるでソファのようなクッションが付いていて座りやすそうな素材が使われている。
机は綺麗に20席並んでおり、正面には教壇と黒板。天井には宝石のような照明。窓の外には美しい庭園の景色が見える。
(あれ、20席……?)
シュンタは気がついた。1クラス40人いるはずなのに、席は縦に4席並んだ列が5列。何度数えても20席しかない。
「な、なんで……?」
シュンタだけでなく他の男子生徒も気づいたらしく、不思議そうな顔を浮かべていた。
そして、そんな私服の男子生徒たちをよそに、黒を基調とした中に美しく赤や金のラインが入ったブレザーとスカートの制服に身を包んだ女子生徒たちはそれらの豪華な席に次々と座っていった。
女子たちは男子と目を合わせることも口を訊くこともないうちに全員が席についた。教室の中は、落ち着いて席についている女子生徒と不安そうな顔を浮かべながら立っている男子生徒というようにくっきりと分かれた。
「はいみんな、進学おめでとう」
そうしていると、教師と思われる女性が教室に入ってきた。手には何かが入った段ボール箱を持っている。
「私の自己紹介は要らないね。高等部からもよろしく。じゃあ早速始めましょう。道具を配るからね」
その女教師も男子生徒に対しては一言も話さず、箱の中身を女子生徒に配り始めた。
女子に配られているものを見ると、それは鎖と首輪、短い乗馬鞭、南京錠とその鍵。そしてもう一つはシュンタには何なのか分からない器具だった。
(なんだあれ、鉄の筒?何に使うんだ?)
「はい、道具は行き渡ったね。じゃあみんな、自分の奴隷を席の隣に連れてきて」
「へ?」
教師の言葉と共に、女生徒たちは立ち上がって男子生徒に近づき、手や髪を掴んで自分の席の近くへと連れていった。
「ほら、早く来なさい」
シュンタの前にも、一人の女子が来てシュンタの服を掴んだ。
その女子はクラスの中で誰よりも美しかった。
背中まで伸びたブラウンの髪、透けるように白い肌。くっきりと通った鼻筋、大きな目。そして
彼女は、シュンタが今まで見た女性の中で最も美しいと思える容姿をしていた。
(……あれ?)
シュンタは一つ疑問に思った。教師は「奴隷を自分の席の近くに」と耳を疑うようなことを言った。そして、女子たちは男子を掴んで自分の席の近くへと連れて行った。
つまり、
「僕達は、奴隷……?」
「フッ!」
シュンタの小さな呟きに、シュンタの服を引いて歩く女子生徒は鼻で笑った。
「そっか、まだ知らされてないんだっけ? あなたたちは」
「え……」
シュンタの心臓がドクンと一度大きく跳ね、一筋の冷や汗が頬を伝った。
「そうよ、あなたたちオスはこの3年間、私たちの奴隷。そして」
その女子生徒は自分の席に座り、顔の前にかかった髪を手で後ろに弾き、長い脚を組んで、言った。
「あなたは3年間、私専用の奴隷よ。二度と普通の生活ができなくなるほど調教してあげるから覚悟しなさい」
「そ、そんな、奴隷なんて……!」
「よし、じゃあ最初の課題。奴隷の服を脱がせて首輪を付けてね。これも点数が付くから真面目にやるのよ!」
シュンタはサヤに反論しようとしたが、きびきびとした教師の声にかき消された。
「シュン。命令よ。服を脱ぎなさい」
サヤはシュンタのことを『シュン』と呼び、命令した。
(な、なんだ、この子……!?)
『服を脱げ』という、相手が応じるわけのない命令を平然と口にした。
その態度はまるで、『自分は圧倒的に上の存在である』と言っているかのような傲慢さ。少なくとも、初対面の同級生への態度ではない。
「ぬ、脱ぐわけないだろ! 突然、服なんて……」
ヒュン……ビシイイイイイイイイン!!!
反論した瞬間、シュンタの太ももにとてつもない衝撃が走った。何かが当たった感触と音。そして一瞬遅れて……
「あ、あ、あ、あがあああああああああ!!!!!」
激痛。太ももにこれまでに感じたことのないような痛みが走り、それは全身へ波紋のように広がっていく。
サヤの手には、先程配られていた短い乗馬鞭があった。
それを使って太ももを叩いたのだとシュンタは理解したが、今もなお引かないこの激痛がサヤの細い腕によって与えられたという事実は信じられなかった。
「次に命令を聞かなかったら、10発連続で折檻するから。命令、『服を脱ぎなさい』」
「あが、ああ……わかり、ました……」
シュンタは冷や汗と涙、そして震えが止まらなくなった。冷や汗と涙は鞭の痛みによるもの。震えはサヤに対する恐怖によるものだった。
平然とありえない命令をしてきて、とてつもない激痛を与えてくる。しかも、断れば10発打ち込まれると言われた。
(こ、こんなのを、10発なんて……)
想像しただけで震えが止まらない。今はこの恐ろしい同級生に逆らわないことが得策であると判断せざるを得なかった。
「ふふ、いい子ね」
シュンタが慌てて服を脱ぎ始めると、サヤは少し笑った。
先程までの冷たい表情と違い、その笑顔は可愛らしい15歳の少女そのものだ。シュンタは少しだけ安心した。
「ただ、さっき一度『反抗』したからね。今夜はお仕置きしてあげる」
「へ……?」
サヤは可愛らしい笑顔のまま、シュンタに言った。
シュンタにはその意味がわからなかったが、サヤはそれ以上何も言わなかったため、会話は終わった。
「あ、あの……ぱ、パンツは……」
「私は『服を脱げ』と命令した。あなたにとって下着は服じゃないのかしら?」
サヤが少し苛ついたような表情で言うと、シュンタの背筋が凍りつくように冷えた。
「ふ、服です! ぬ、脱ぎます……」
シュンタが恥ずかしそうにパンツに手をかけて脱いだが、その中身、露わになった男性器にサヤは一切の関心を示さなかった。
「首を貸しなさい」
サヤはそう言うと、全裸のシュンタの髪を掴んで自分の方に引き寄せた。
「うっ……」
髪を引かれた痛みでシュンタは声をあげたが、サヤはそれに構うことなく、机の上に置いてあった首輪をシュンタに付けた。
そして、その首輪に鎖を繋ぎ、鎖の先を手に持った。サヤが持つ側の鎖には革製の柄が付いている。
「先生、終わりました」
「あら伊集院さん、早いのね。他の子も見習いなさい」
「おい!! ふざけんなよ!!!」
サヤが課題の終了を報告し、教師がそれに応えると同時に、教室内に怒号が響いた。
「俺は普通にここに入学してきただけなんだよ!! なんで奴隷なんかやんなきゃなんねぇんだ!!」
クラス中の視線を集めたのは、頭を金髪に染めた男子生徒。
その目の前にいる少しピンクがかった柔らかな色の髪をウェーブにした可愛らしい雰囲気の女子生徒に、今にも噛みつきそうな勢いで男子生徒は怒鳴っていた。
「だからー、何回も説明してるじゃないですかぁ。あなたは3年間、私の奴隷なんですよぉ〜」
「だから、それが納得できねぇって言ってんじゃねぇか!」
「もぉ〜、分からずやさんなんだから。ケンちゃんは〜」
「誰がケンちゃんだコラァ!」
彼の名はケンタロウ。地元の中学では名の知れた不良であり、成績が悪くどこの高校にも行けなかったため、ここに入学してきている。
「あら、モモカったら。ずいぶん喧しいのを選んだのね。他にもたくさん選べたはずなのに」
「……?」
シュンタはサヤが呟いた言葉を聞いたが、意味はよく分からなかった。一つだけ理解できたのは、どうやらあの緩い雰囲気の女子は「モモカ」という名前だということ。
「も〜、モモちゃん怒ったぞ! そんな悪い子にはお仕置き♡」
そう言ってモモカが鞭を持つと、ケンタロウは「なんだ! やんのか!?」と構えた。
拳を構えたケンタロウ。その姿を他の女子たちは冷めた目で見つめ、既に服を脱がされた、もしくは脱いでいる途中の男子達は期待を込めてケンタロウを見つめた。
ここでケンタロウが勝てば、この状況から抜け出すきっかけが生まれるかもしれない。
しかし、そんな期待はあっさりと散ることになった。
ヒュオン、ビシィン! バシィン! ズパァン!
まるで優雅な指揮者のようにモモカは鞭を振るった。ケンタロウはそれを一発も防ぐことは叶わず、脚、脇腹、顔に鞭を受けた。
「あ、うぎゃああああああああ!! 痛えぇぇぇええええ!!!」
ケンタロウはたまらず、床に蹲って声をあげた。
「あら、ケンちゃんはもうおしまいですか? あと、鞭を持った相手に対して背中を見せるのは……」
ヒュオン……ビシイイイイイイイイン!!!
モモカは思い切り、ケンタロウの背中に鞭を振り下ろした。
「とっても危ないんですよ?」
「うぎゃあああああああああああああああ!!!」
ケンタロウは最初に打たれた3箇所ととどめの一発を受けた背中の激痛に泣き叫んだ。
「はいケンちゃん。二度目の命令です。服を脱いでくださいね♡」
「わ、わかり、ました……だからもう、打たないで……」
ケンタロウはそう言うと、涙を流し鼻水を啜りながら服を脱ぎ、モモカの手によって首輪を装着させられた。
「よし、全員終わったね。じゃあ今日の課題は『奴隷に現実を教える』ことだから、部屋でしっかりと課題に取り組むように。解散」
教師がそう言って教室を出ていくと、女子生徒たちはそれぞれの奴隷を引き連れて寮へ向かった。
サヤはシュンタに「ついてきなさい」と一言だけ告げ、鎖を引いて教室から女子寮の方へと歩き始めた。
サヤとシュンタだけでなく、他の女子も全員が裸の男子に首輪を付けて鎖で連れている。異様な光景には違いなく、男子は全員が恐怖や焦りの表情を浮かべていたが、女子は平然としている者が大半だった。
中には、
「うふふ! ケンちゃん、これからたあっぷり可愛がってあげますからね〜♡」
笑顔を浮かべ、これからの学園生活に心を躍らせている者もいた。
モモカに連れられたケンタロウは、まだ納得していないのか、「クソが……!」と小さく呟いてモモカを睨みつけていた。
校舎を出て、広大な黒椿学園の敷地内を歩いていくと、「学生寮」と書かれたプレートの立つ大きな建物の前に着いた。
その建物はさながらタワーマンションで、黒椿学園の財力を物語っているようでもあった。
「あ、あの……僕は、その、男子の、寮に……」
シュンタは慌てて言った。早く男子寮に行きたい。男子たちと話がしたい。これからの打開策、脱出の作戦を立てなければならない。少なくとも、あのケンタロウという男は協力してくれるはず。
「男子寮? そんなものはないけど?」
サヤはシュンタに対して、何を言っているのかと言わんばかりの表情で告げた。
「え!? でも、パンフレットには二人部屋だって……」
そう、二人部屋ということは同性のルームメイトがいるはず。
答えることなく、サヤはシュンタを連れたまま女子寮の中に入った。
豪華なエントランスを抜けてエレベーターに乗り込み、25までのボタンが並んでいる中から20のボタンを押した。
「……なるほど。男子用のパンフレットにはそう書いてあるのね」
サヤは少し思考して納得し、結論を出した。
「そうね。確かにそういう解釈もあるわね。ただ、女子のパンフレットにはそうは書いてないの」
サヤはエレベーターを降り、「2005」と書かれた部屋の前で立ち止まり、カバンからカードキーを取り出してドアにスキャンした。
「女子のパンフレットにはこう書いてあるわ」
ドアがガチャンと音を立ててロックが解除され、サヤは部屋の中に入った。
「『完全個室、奴隷付き』……ってね」
「そ、そんな……じゃあ、僕は……」
(奴隷ってことか……!? でも、そんなの絶対認めないぞ……!)
部屋に入ると、目の前の廊下にはキッチンが併設され、進んだ先は12畳ほどの広めの1ルームになっていた。
「ここで、暮らすのか……」
シュンタは部屋の中を見回した。玄関に入ってすぐ右手にはキッチン。左手にはバスとトイレ。
奥の部屋には本棚や机、ベッドなどの家具が置かれている。
一見すると普通の部屋。
「……ん?」
しかしシュンタは妙なものを見つけた。部屋に入ってすぐ左の壁に、赤く塗られたX字型の板が貼り付けてある。かなり大きなもので、足を開き両手を上げて立っている人間の形にも見える。
そして、その板の右上、左上、右下、左下には金属製の輪のようなものが取り付けてある。
X字型の板の下の部分、板の形を人に例えるならば股の下辺りには、小さな扉のようなものがあった。
犬や猫の通り道のように低い位置にある小さなその扉の奥は、暗くなっていてよく見えない。ギリギリ四つん這いの人間が通れそうな大きさだが、何に使うのだろうか。
(何かを収納するのかな……服とか……?)
これから自分が暮らす部屋。不気味な道具や扉もあるが、なかなか悪くないとシュンタは考えた。
部屋の中に女子が常にいるという緊張感はあるが、この部屋はなかなか広く、二人で生活しても狭くは感じないだろう。
「あ、あれ……?」
シュンタはとあることに気付いた。
「ベッドが、一つしかない……?」
「ふっ、あはは!」
シュンタが呟いた瞬間、サヤは突然笑い始めた。
「あなた、自分がベッドで寝られるとでも思っていたの?」
サヤは笑いながらシュンタに近づき、シュンタの腹を手で強く押した。
「ううっ!」
シュンタは先程の赤いX字型の板がある方向に突き飛ばされた。
「あなたはまだ全然状況が掴めてないようね。いいわ。しっかり教えてあげる。奴隷に現実を教えるのが今日の課題だしね」
サヤはそう言うと、シュンタの手を掴んで持ち上げ、その手をX字型の板に取り付けられている金属の輪に固定した。
ガチャン!
「うっ!?」
音を立ててロックがかかり、シュンタは手を動かせなくなった。
シュンタが動揺している間に、サヤは手際良く両手両足をX字型の板に拘束してしまった。
「じゃあ……そうね。あなたが何故こんな状況になったのかを説明してあげる。ただし……」
サヤは部屋の中の机の引き出しの中から、一本の鞭を取り出した。
それは教室で使っていた短い乗馬鞭ではない。黒くて長い蛇の様な、革製の一本鞭だ。
「教室で私の命令に一度背いたことへの、お仕置きをしながらね!」
「よし、じゃあ最初の課題。奴隷の服を脱がせて首輪を付けてね。これも点数が付くから真面目にやるのよ!」
シュンタはサヤに反論しようとしたが、きびきびとした教師の声にかき消された。
「シュン。命令よ。服を脱ぎなさい」
サヤはシュンタのことを『シュン』と呼び、命令した。
(な、なんだ、この子……!?)
『服を脱げ』という、相手が応じるわけのない命令を平然と口にした。
その態度はまるで、『自分は圧倒的に上の存在である』と言っているかのような傲慢さ。少なくとも、初対面の同級生への態度ではない。
「ぬ、脱ぐわけないだろ! 突然、服なんて……」
ヒュン……ビシイイイイイイイイン!!!
反論した瞬間、シュンタの太ももにとてつもない衝撃が走った。何かが当たった感触と音。そして一瞬遅れて……
「あ、あ、あ、あがあああああああああ!!!!!」
激痛。太ももにこれまでに感じたことのないような痛みが走り、それは全身へ波紋のように広がっていく。
サヤの手には、先程配られていた短い乗馬鞭があった。
それを使って太ももを叩いたのだとシュンタは理解したが、今もなお引かないこの激痛がサヤの細い腕によって与えられたという事実は信じられなかった。
「次に命令を聞かなかったら、10発連続で折檻するから。命令、『服を脱ぎなさい』」
「あが、ああ……わかり、ました……」
シュンタは冷や汗と涙、そして震えが止まらなくなった。冷や汗と涙は鞭の痛みによるもの。震えはサヤに対する恐怖によるものだった。
平然とありえない命令をしてきて、とてつもない激痛を与えてくる。しかも、断れば10発打ち込まれると言われた。
(こ、こんなのを、10発なんて……)
想像しただけで震えが止まらない。今はこの恐ろしい同級生に逆らわないことが得策であると判断せざるを得なかった。
「ふふ、いい子ね」
シュンタが慌てて服を脱ぎ始めると、サヤは少し笑った。
先程までの冷たい表情と違い、その笑顔は可愛らしい15歳の少女そのものだ。シュンタは少しだけ安心した。
「ただ、さっき一度『反抗』したからね。今夜はお仕置きしてあげる」
「へ……?」
サヤは可愛らしい笑顔のまま、シュンタに言った。
シュンタにはその意味がわからなかったが、サヤはそれ以上何も言わなかったため、会話は終わった。
「あ、あの……ぱ、パンツは……」
「私は『服を脱げ』と命令した。あなたにとって下着は服じゃないのかしら?」
サヤが少し苛ついたような表情で言うと、シュンタの背筋が凍りつくように冷えた。
「ふ、服です! ぬ、脱ぎます……」
シュンタが恥ずかしそうにパンツに手をかけて脱いだが、その中身、露わになった男性器にサヤは一切の関心を示さなかった。
「首を貸しなさい」
サヤはそう言うと、全裸のシュンタの髪を掴んで自分の方に引き寄せた。
「うっ……」
髪を引かれた痛みでシュンタは声をあげたが、サヤはそれに構うことなく、机の上に置いてあった首輪をシュンタに付けた。
そして、その首輪に鎖を繋ぎ、鎖の先を手に持った。サヤが持つ側の鎖には革製の柄が付いている。
「先生、終わりました」
「あら伊集院さん、早いのね。他の子も見習いなさい」
「おい!! ふざけんなよ!!!」
サヤが課題の終了を報告し、教師がそれに応えると同時に、教室内に怒号が響いた。
「俺は普通にここに入学してきただけなんだよ!! なんで奴隷なんかやんなきゃなんねぇんだ!!」
クラス中の視線を集めたのは、頭を金髪に染めた男子生徒。
その目の前にいる少しピンクがかった柔らかな色の髪をウェーブにした可愛らしい雰囲気の女子生徒に、今にも噛みつきそうな勢いで男子生徒は怒鳴っていた。
「だからー、何回も説明してるじゃないですかぁ。あなたは3年間、私の奴隷なんですよぉ〜」
「だから、それが納得できねぇって言ってんじゃねぇか!」
「もぉ〜、分からずやさんなんだから。ケンちゃんは〜」
「誰がケンちゃんだコラァ!」
彼の名はケンタロウ。地元の中学では名の知れた不良であり、成績が悪くどこの高校にも行けなかったため、ここに入学してきている。
「あら、モモカったら。ずいぶん喧しいのを選んだのね。他にもたくさん選べたはずなのに」
「……?」
シュンタはサヤが呟いた言葉を聞いたが、意味はよく分からなかった。一つだけ理解できたのは、どうやらあの緩い雰囲気の女子は「モモカ」という名前だということ。
「も〜、モモちゃん怒ったぞ! そんな悪い子にはお仕置き♡」
そう言ってモモカが鞭を持つと、ケンタロウは「なんだ! やんのか!?」と構えた。
拳を構えたケンタロウ。その姿を他の女子たちは冷めた目で見つめ、既に服を脱がされた、もしくは脱いでいる途中の男子達は期待を込めてケンタロウを見つめた。
ここでケンタロウが勝てば、この状況から抜け出すきっかけが生まれるかもしれない。
しかし、そんな期待はあっさりと散ることになった。
ヒュオン、ビシィン! バシィン! ズパァン!
まるで優雅な指揮者のようにモモカは鞭を振るった。ケンタロウはそれを一発も防ぐことは叶わず、脚、脇腹、顔に鞭を受けた。
「あ、うぎゃああああああああ!! 痛えぇぇぇええええ!!!」
ケンタロウはたまらず、床に蹲って声をあげた。
「あら、ケンちゃんはもうおしまいですか? あと、鞭を持った相手に対して背中を見せるのは……」
ヒュオン……ビシイイイイイイイイン!!!
モモカは思い切り、ケンタロウの背中に鞭を振り下ろした。
「とっても危ないんですよ?」
「うぎゃあああああああああああああああ!!!」
ケンタロウは最初に打たれた3箇所ととどめの一発を受けた背中の激痛に泣き叫んだ。
「はいケンちゃん。二度目の命令です。服を脱いでくださいね♡」
「わ、わかり、ました……だからもう、打たないで……」
ケンタロウはそう言うと、涙を流し鼻水を啜りながら服を脱ぎ、モモカの手によって首輪を装着させられた。
「よし、全員終わったね。じゃあ今日の課題は『奴隷に現実を教える』ことだから、部屋でしっかりと課題に取り組むように。解散」
教師がそう言って教室を出ていくと、女子生徒たちはそれぞれの奴隷を引き連れて寮へ向かった。
サヤはシュンタに「ついてきなさい」と一言だけ告げ、鎖を引いて教室から女子寮の方へと歩き始めた。
サヤとシュンタだけでなく、他の女子も全員が裸の男子に首輪を付けて鎖で連れている。異様な光景には違いなく、男子は全員が恐怖や焦りの表情を浮かべていたが、女子は平然としている者が大半だった。
中には、
「うふふ! ケンちゃん、これからたあっぷり可愛がってあげますからね〜♡」
笑顔を浮かべ、これからの学園生活に心を躍らせている者もいた。
モモカに連れられたケンタロウは、まだ納得していないのか、「クソが……!」と小さく呟いてモモカを睨みつけていた。
校舎を出て、広大な黒椿学園の敷地内を歩いていくと、「学生寮」と書かれたプレートの立つ大きな建物の前に着いた。
その建物はさながらタワーマンションで、黒椿学園の財力を物語っているようでもあった。
「あ、あの……僕は、その、男子の、寮に……」
シュンタは慌てて言った。早く男子寮に行きたい。男子たちと話がしたい。これからの打開策、脱出の作戦を立てなければならない。少なくとも、あのケンタロウという男は協力してくれるはず。
「男子寮? そんなものはないけど?」
サヤはシュンタに対して、何を言っているのかと言わんばかりの表情で告げた。
「え!? でも、パンフレットには二人部屋だって……」
そう、二人部屋ということは同性のルームメイトがいるはず。
答えることなく、サヤはシュンタを連れたまま女子寮の中に入った。
豪華なエントランスを抜けてエレベーターに乗り込み、25までのボタンが並んでいる中から20のボタンを押した。
「……なるほど。男子用のパンフレットにはそう書いてあるのね」
サヤは少し思考して納得し、結論を出した。
「そうね。確かにそういう解釈もあるわね。ただ、女子のパンフレットにはそうは書いてないの」
サヤはエレベーターを降り、「2005」と書かれた部屋の前で立ち止まり、カバンからカードキーを取り出してドアにスキャンした。
「女子のパンフレットにはこう書いてあるわ」
ドアがガチャンと音を立ててロックが解除され、サヤは部屋の中に入った。
「『完全個室、奴隷付き』……ってね」
「そ、そんな……じゃあ、僕は……」
(奴隷ってことか……!? でも、そんなの絶対認めないぞ……!)
部屋に入ると、目の前の廊下にはキッチンが併設され、進んだ先は12畳ほどの広めの1ルームになっていた。
「ここで、暮らすのか……」
シュンタは部屋の中を見回した。玄関に入ってすぐ右手にはキッチン。左手にはバスとトイレ。
奥の部屋には本棚や机、ベッドなどの家具が置かれている。
一見すると普通の部屋。
「……ん?」
しかしシュンタは妙なものを見つけた。部屋に入ってすぐ左の壁に、赤く塗られたX字型の板が貼り付けてある。かなり大きなもので、足を開き両手を上げて立っている人間の形にも見える。
そして、その板の右上、左上、右下、左下には金属製の輪のようなものが取り付けてある。
X字型の板の下の部分、板の形を人に例えるならば股の下辺りには、小さな扉のようなものがあった。
犬や猫の通り道のように低い位置にある小さなその扉の奥は、暗くなっていてよく見えない。ギリギリ四つん這いの人間が通れそうな大きさだが、何に使うのだろうか。
(何かを収納するのかな……服とか……?)
これから自分が暮らす部屋。不気味な道具や扉もあるが、なかなか悪くないとシュンタは考えた。
部屋の中に女子が常にいるという緊張感はあるが、この部屋はなかなか広く、二人で生活しても狭くは感じないだろう。
「あ、あれ……?」
シュンタはとあることに気付いた。
「ベッドが、一つしかない……?」
「ふっ、あはは!」
シュンタが呟いた瞬間、サヤは突然笑い始めた。
「あなた、自分がベッドで寝られるとでも思っていたの?」
サヤは笑いながらシュンタに近づき、シュンタの腹を手で強く押した。
「ううっ!」
シュンタは先程の赤いX字型の板がある方向に突き飛ばされた。
「あなたはまだ全然状況が掴めてないようね。いいわ。しっかり教えてあげる。奴隷に現実を教えるのが今日の課題だしね」
サヤはそう言うと、シュンタの手を掴んで持ち上げ、その手をX字型の板に取り付けられている金属の輪に固定した。
ガチャン!
「うっ!?」
音を立ててロックがかかり、シュンタは手を動かせなくなった。
シュンタが動揺している間に、サヤは手際良く両手両足をX字型の板に拘束してしまった。
「じゃあ……そうね。あなたが何故こんな状況になったのかを説明してあげる。ただし……」
サヤは部屋の中の机の引き出しの中から、一本の鞭を取り出した。
それは教室で使っていた短い乗馬鞭ではない。黒くて長い蛇の様な、革製の一本鞭だ。
「教室で私の命令に一度背いたことへの、お仕置きをしながらね!」
「ひ、ヒッ!」
シュンタはあまりの恐怖に小さく悲鳴をあげた。
「私が鞭を打ったら数を数えなさい。100回打ち込んだらお仕置きは終わりにしてあげる」
「は、はひ……?」
シュンタは状況を全く理解できていなかった。何故自分はここに拘束され、鞭打たれることになっているのか。
「じゃ、いくよ」
ヒュオンッ……
白く小さな手に握られた真っ黒な蛇が、宙を舞った。
ビシイイイイイイイイン!!!
美しく舞うその蛇は、突如加速してシュンタの脇腹を食いちぎるように咬みついた。
「い、い、い、いぎああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!」
これまで感じたこともなく、そして、普通に生きていればこの先感じることもないような激痛。
痛い。痛い。痛い。
それ以外考えられない。
呼吸ができない。汗が止まらない。震えが止まらない。
脇腹から全身にかけて激痛の津波が広がっていく。脳が命令する。「今すぐ逃げろ」「この女から離れろ」と。
しかしそれは叶わない。
ガチャガチャガチャ!
渾身の力で逃げようとしても、拘束具が僅かに音を立てるだけ。逃げられない。つまり、
「数を数えなさいと言ったでしょ。今のは無しね。あと100回」
この女が許すまで打たれる。
このあり得ないような、耐え難い激痛を、あと100回与えられる。
「い、嫌だ! 許してください! なんでも言うこと聞きますから! もう鞭はいやだ!」
「いいえ、許さない。私への反抗は鞭打ち100回。そして、今のも反抗ね。100回追加であと200回打ち込むから」
絶望。あまりにも大きく、深い絶望。
目の前の女子高生に少し意見しただけで、あのおぞましいほどの激痛をさらに100回受けなければならない。
あまりにも容易く、軽く与えられる巨大な絶望。
「ゆ、許してくださいぃ……」
「許さないと言っているでしょ。私に反抗したらどうなるかを、その身に刻んであげる」
ヒュオンッ!
再び、黒蛇が宙を舞う。
「ヒッ、ヒイッ!」
シュンタはあまりの恐怖に悲鳴をあげるが、その恐怖を与えるサヤの表情は変わらない。
ビシイイイイイイイイイイイイイイン!!
「うぎゃあああああああああああああああああああああああああああ!!!!」
脚に、二発目の鞭が打ち込まれる。
気が狂いそうな激痛。叫ぶ。歯を食いしばる。目を固く瞑る。様々なことを試してみるがその激痛は誤魔化せない。逃れられない。シュンタの体の中に入って暴れ回る。
「い、いちいいい!」
シュンタは先程言われたことを思い出し、慌てて「1」と数えた。
「そう。しっかりと数えなさい。あと199回よ」
シュンタはあまりの恐怖に小さく悲鳴をあげた。
「私が鞭を打ったら数を数えなさい。100回打ち込んだらお仕置きは終わりにしてあげる」
「は、はひ……?」
シュンタは状況を全く理解できていなかった。何故自分はここに拘束され、鞭打たれることになっているのか。
「じゃ、いくよ」
ヒュオンッ……
白く小さな手に握られた真っ黒な蛇が、宙を舞った。
ビシイイイイイイイイン!!!
美しく舞うその蛇は、突如加速してシュンタの脇腹を食いちぎるように咬みついた。
「い、い、い、いぎああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!」
これまで感じたこともなく、そして、普通に生きていればこの先感じることもないような激痛。
痛い。痛い。痛い。
それ以外考えられない。
呼吸ができない。汗が止まらない。震えが止まらない。
脇腹から全身にかけて激痛の津波が広がっていく。脳が命令する。「今すぐ逃げろ」「この女から離れろ」と。
しかしそれは叶わない。
ガチャガチャガチャ!
渾身の力で逃げようとしても、拘束具が僅かに音を立てるだけ。逃げられない。つまり、
「数を数えなさいと言ったでしょ。今のは無しね。あと100回」
この女が許すまで打たれる。
このあり得ないような、耐え難い激痛を、あと100回与えられる。
「い、嫌だ! 許してください! なんでも言うこと聞きますから! もう鞭はいやだ!」
「いいえ、許さない。私への反抗は鞭打ち100回。そして、今のも反抗ね。100回追加であと200回打ち込むから」
絶望。あまりにも大きく、深い絶望。
目の前の女子高生に少し意見しただけで、あのおぞましいほどの激痛をさらに100回受けなければならない。
あまりにも容易く、軽く与えられる巨大な絶望。
「ゆ、許してくださいぃ……」
「許さないと言っているでしょ。私に反抗したらどうなるかを、その身に刻んであげる」
ヒュオンッ!
再び、黒蛇が宙を舞う。
「ヒッ、ヒイッ!」
シュンタはあまりの恐怖に悲鳴をあげるが、その恐怖を与えるサヤの表情は変わらない。
ビシイイイイイイイイイイイイイイン!!
「うぎゃあああああああああああああああああああああああああああ!!!!」
脚に、二発目の鞭が打ち込まれる。
気が狂いそうな激痛。叫ぶ。歯を食いしばる。目を固く瞑る。様々なことを試してみるがその激痛は誤魔化せない。逃れられない。シュンタの体の中に入って暴れ回る。
「い、いちいいい!」
シュンタは先程言われたことを思い出し、慌てて「1」と数えた。
「そう。しっかりと数えなさい。あと199回よ」
「……ふぅ。シュン。私に逆らうとどうなるのか……よくわかったかしら?」
「は……はい……サヤ様……に、二度と、逆らいません……」
シュンタは体の芯から震え、奥歯をガタガタと鳴らしていた。
シュンタは全身を傷つけられ、出血・打撲は著しく、打ち込まれた200発の鞭痕からは今もなお激痛が全身へ広がっている。
裂けた皮膚。腫れ上がった肉。擦り下ろされた心。
震えが止まらない。自然とサヤのことを『サヤ様』と呼んでしまう。この人には逆らえない。絶対に逆らってはいけない。体と心に強く刻み込まれた。
今回刻まれた『恐怖』はこの先ずっと、永遠にシュンタの心を縛る。サヤを明確に「上」と認め、自分を「下」と認識してしまった。
(……このくらいで良いのかしら?)
サヤは目の前で震えている男を見て、少し不安を覚えていた。
というのも、サヤにとっても調教の『実践』はこれが初めて。
初めて与えられた「自分のオス」を鞭で打つのが思いの外楽しく、少しハイになっていたサヤだが、打ち終わって冷静になると若干の不安な気持ちが出てきた。
中等部の調教理論では、「オスは女よりも力が強い。その分便利な所も多いが、反抗されると危険も伴う」と習った。
そして、オスに反抗されないための対策は二つ。一つは襲い掛かられても身を守る為の護身術。そしてもう一つは
「痛い……痛いよぉ……うぐ、ゴホッ……ううう……」
鞭などで苦痛を与えることによる、徹底的な『上下関係』の仕込み。
主人に逆らうとどうなるのか。それを徹底的に体に教える。激痛を与え、逆らうとそうなるのだと教え込んでおけば、オスは逆らわなくなる。
具体的な鞭打ちの数までは習わなかった。何故なら奴隷によって必要な数は異なるからだ。
(もっと打ち込んだ方が良い……? いや、既にかなりのダメージがある。日常生活に影響が出るほど打ち込むのは逆効果。動けなくしてしまえば、この子のオス奴隷としての価値を失わせることになる)
そう。殺したり動けなくしたりしてしまうのは、調教の成績としては下の下。何故ならオス奴隷は「女性が便利に使うために存在する」。だから、与えられた仕事や上位の人間への奉仕をできない状態にするのは本来の目的を外れた行為。
(そうだ、奉仕。これも教えないと……)
サヤは中等部での授業を思い出し、立ち上がった。
「……トイレに行きたくなっちゃった。シュン、ついてきなさい」
奴隷には主人である自分の「迷い」や「不安」を見せてはいけない。だからあくまで堂々と、それが当然であるかのようにサヤは命じた。
「は……はい……サヤ様……に、二度と、逆らいません……」
シュンタは体の芯から震え、奥歯をガタガタと鳴らしていた。
シュンタは全身を傷つけられ、出血・打撲は著しく、打ち込まれた200発の鞭痕からは今もなお激痛が全身へ広がっている。
裂けた皮膚。腫れ上がった肉。擦り下ろされた心。
震えが止まらない。自然とサヤのことを『サヤ様』と呼んでしまう。この人には逆らえない。絶対に逆らってはいけない。体と心に強く刻み込まれた。
今回刻まれた『恐怖』はこの先ずっと、永遠にシュンタの心を縛る。サヤを明確に「上」と認め、自分を「下」と認識してしまった。
(……このくらいで良いのかしら?)
サヤは目の前で震えている男を見て、少し不安を覚えていた。
というのも、サヤにとっても調教の『実践』はこれが初めて。
初めて与えられた「自分のオス」を鞭で打つのが思いの外楽しく、少しハイになっていたサヤだが、打ち終わって冷静になると若干の不安な気持ちが出てきた。
中等部の調教理論では、「オスは女よりも力が強い。その分便利な所も多いが、反抗されると危険も伴う」と習った。
そして、オスに反抗されないための対策は二つ。一つは襲い掛かられても身を守る為の護身術。そしてもう一つは
「痛い……痛いよぉ……うぐ、ゴホッ……ううう……」
鞭などで苦痛を与えることによる、徹底的な『上下関係』の仕込み。
主人に逆らうとどうなるのか。それを徹底的に体に教える。激痛を与え、逆らうとそうなるのだと教え込んでおけば、オスは逆らわなくなる。
具体的な鞭打ちの数までは習わなかった。何故なら奴隷によって必要な数は異なるからだ。
(もっと打ち込んだ方が良い……? いや、既にかなりのダメージがある。日常生活に影響が出るほど打ち込むのは逆効果。動けなくしてしまえば、この子のオス奴隷としての価値を失わせることになる)
そう。殺したり動けなくしたりしてしまうのは、調教の成績としては下の下。何故ならオス奴隷は「女性が便利に使うために存在する」。だから、与えられた仕事や上位の人間への奉仕をできない状態にするのは本来の目的を外れた行為。
(そうだ、奉仕。これも教えないと……)
サヤは中等部での授業を思い出し、立ち上がった。
「……トイレに行きたくなっちゃった。シュン、ついてきなさい」
奴隷には主人である自分の「迷い」や「不安」を見せてはいけない。だからあくまで堂々と、それが当然であるかのようにサヤは命じた。
部屋から出て、玄関へと続く廊下にあるドアは二つ。一つは洗面所、バスルームへと続く扉。そしてもう一つは『Toilet』と書かれた扉。
「私がトイレに行くときはあなたは必ず同行。それは絶対よ。覚えておきなさい」
「は、はい……」
シュンタには意味がわからなかった。「トイレ」と言えば、通常は必ず男女別。それなのに、なぜ同行させられるのか。
サヤがガチャリとトイレのドアを開け、手に持っているシュンタの首輪に繋がる鎖を引いた。
「何してるの。早く入りなさい」
「え……?」
シュンタは驚いた。なぜなら、てっきりドアの前で待機させられるのだと考えていたからだ。
「あ、あの……い、いいん、ですか……?」
シュンタは女性が便器に座って用を足す部屋の中に男である自分がいてもいいはずがないと考え、恐る恐る言った。
「クスッ。もしかして『男だから一緒に入れない』とか考えてる?」
「は、はい……だって、女の子が、男とトイレなんて……」
「この学園に『男』なんていない。ここにいるのは『女性』と『オス』のみ。あなた達は男じゃなくてオス。つまり動物と同じ。ペットのオス犬の前でトイレを恥ずかしがる女性がいるかしら?」
「そ、そんなぁ……」
この学園では自分は「男」とさえも呼ばれない。奴隷は動物や道具扱いで、「オス」。あまりにも横暴な考え方だとシュンタは感じた。
「ま、そんなことはどうでも良いわ。これからあなたがこれから三年間、私に行う奉仕の一つを教えるから。一度で覚えなさい」
シュンタはそう言われ、トイレの中に鎖で引き込まれた。
「は、はい……」
(なんだろう……トイレ掃除とかかな?)
シュンタが呑気な想像をしているのをよそに、サヤはトイレに入るとまず制服のスカートの中に手を入れ、パンツを下げた。
「う、うわ! そんな....!?」
シュンタは今日会ったばかりの女子が突然目の前で下着を脱いだのを見て声をあげた。
「何を驚いてるの。私はただトイレをするだけよ。あなたはそこに座りなさい」
サヤは平然とした顔でそう言って、洋式便器の前にある床を指でさした。
サヤはこれに関しては特に羞恥は無かった。三年前、黒椿学園に入学したばかりの中学一年生の時はこの行為に強い恥じらいを覚える自分もいた気がするが、中学の三年間で何度も繰り返してきた今は何とも思わない。
既に、目の前にオスを座らせて行うこれこそが自然な排泄のスタイルだと考えているところもある。
「よいしょ……」
サヤはスカートを捲り上げ、洋式便器に腰を下ろした。そして
ジョオオオオオオオオ……
「ふぅ……」
小便を、排泄した。ごくごく自然に、いつも通りに。
「あ、あ、あああぁぁぁ……」
目の前で、女性が排泄している。その異様な光景にシュンタは目を剥いた。思わず凝視してしまう。足首まで下げられたサヤのパンツを。水音を発しているサヤの股を。
(そうか。このオスの反応は当たり前か。外の世界で女性は個室で一人。終わったら『お股をトイレットペーパーで拭く』んだ。ふふ……私にはもう、そんなことはできないな。多分)
「ん……ふう……」
排泄を終えたサヤは小さな息を吐き、シュンタの方に向き直った。
「シュン。今からやるのはあなたたち奴隷の奉仕の一つ、『ビデ』よ」
「び、びで……?」
「そう。女性がオシッコをしたらお股を拭いて綺麗にしなきゃならないでしょう? あなたが主人である私のお股を綺麗にするのよ」
「あ、は、はい……」
サヤの命令に、シュンタに少し緊張が走った。そしてそれと同時に疑問も湧いた。
(要は、トイレットペーパーでサヤ様のお股を拭けってことか……あれ?)
「あ、あの、サヤ様……トイレット、ペーパーは……?」
「ああ、この学園には一つもないでしょうね。だって……」
サヤは左手でシュンタの髪を掴み、右手の親指と人差し指をシュンタの口の中に入れ、舌を摘んだ。
「私たちのトイレの後は、これで綺麗にするんだから」
「は、はひ……?」
パンツを脱いで下半身を露出させている排泄後のサヤに舌を掴まれたシュンタは、意味がわからないといった顔で情けなくサヤを見上げた。
「あなたたちオス奴隷は、私たち女性が排泄したらそこを舐め清めるのよ。それはこの学園では常識。ふふっ、これを覚えちゃうと普通のウォシュレットじゃ物足りないし、トイレットペーパーなんてもってのほか。やみつきになるのよね」
黒椿学園の卒業生には、卒業後に経営者や政治家となって活動している女性が多くいるが、いずれもが必ず「男性秘書」を従えていた。
その理由は必ずといっていいほど、この「排泄後の処理」のため。
黒椿学園の女生徒は中等部、高等部と6年間トイレ後にこの方法で秘部を綺麗にする。
その習慣が体に根付くので、卒業後もつい「男に舐めさせて拭く」以外の処理方法を避けてしまうのだ。
だから彼女たちはこの黒椿学園で身につけた調教技術を駆使して男を捕らえ、あるいは購入して調教する。排泄後に舐めさせるための男は何としても確保するのだ。
この方法には様々なメリットがあり、6年間でほぼ全ての女生徒が虜になってしまう。
「肌荒れしない、保湿できる、自動で動く、柔らかい、奴隷が直接見てするから丁寧に掃除できる。そして何より……ふふっ!」
サヤはシュンタの頭を掴み、シュンタの口を無理やり自分の性器にあてがった。
(惨めな奴隷の顔……ゾクゾクする……!)
サヤは生来のサディストではない。そしてサヤ同様、この学園に入学してくる女子のほとんどに元々Sの気質はなかった。
そもそも、まだ性にも目覚めていない中学1年生が「サディスト」であるわけもない。だから、黒椿学園は彼女達が将来オス奴隷を扱えるよう、彼女たちの心をSに目覚めさせる教育をしなければならない。
その方法として効果的なのが、この排泄後の舐め掃除。
人間の顔は、上目遣いをした際に最も弱々しく見える。
そして小便を舐め取らされる惨めさから、その目に涙でも溜まっていればさらに悲壮感が増す。
そのような情けない表情で見上げられながら、性感帯である性器を舐めさせる。
黒椿学園に入学したばかりの中学1年生の女生徒は、危険がないように、護身術を身につけるまでは主に幼い8〜11歳の奴隷で調教の練習をする。
サヤが初めて性器を舐めさせたのは8歳の奴隷。自分の前に跪いた奴隷が性器を舐めながら、涙目の上目遣いでサヤを見たその瞬間、サヤは背筋がゾワリと震えたのを覚えている。
そして何度か舐めさせた頃には「自分より弱い者を虐げる快感」に目覚めていた。
サヤ以外の女生徒達も、それまでは良家のお嬢様として育てられ、花を愛でるような優しい眼差しを持っていたが、何度もそうやって目の前に弱った獲物を用意され、可愛らしい奴隷に舐めさせた後には、弱者を甚振る肉食獣の目付きに変わっていた。
これが黒椿学園の教育方針。まずは「サディスト」として開花させる。弱者を踏みつけ、強者として振る舞うのが常であるように、彼女たちに教え込むのだ。
中等部で3年間教育を受け高等部に入学する頃には、優しく愛に溢れた「お嬢様」たちは、全員が厳しく奴隷に鞭を入れる「女王様」へと変貌していた。
「い、嫌です! こんなところ、おしっこの後なんて、汚いのに舐めるなんて……」
パァン!!
シュンタがそう言って抵抗の素振りを見せた瞬間、サヤの右手はシュンタの頬をビンタしていた。
「うぶっ!!」
自分の股を舐めない奴隷にビンタをする。それはサヤにとってあまりにも当たり前の行為で、殴られた痛みに驚いているシュンタとは対照的にサヤは冷静な表情だった。
「今のは警告。次に拒否したら『お仕置き』する。あなたがまた私の鞭の餌食になりたいのなら、どうぞ」
「あ、ああ、ああああああ……」
『お仕置き』という言葉を聞いただけで、シュンタの体の震えと涙が止まらなくなった。
(な、なんだ、これ……? ただ、『お仕置き』って言われただけなのに……?)
シュンタの頭には抵抗したい気持ちがあっても、体が全く言うことを聞かなかった。震えは止まらず、サヤの顔を情けない顔で見上げることしかできない。
「あ、あう、ああ、わかり、ました……」
シュンタはどうしても『お仕置き』だけは受けたくないと思い、諦めて舌を出し、サヤの股に顔を近づけた。
そしてシュンタが舐めようとしたのを見て、サヤは腰を前に突き出した。
(う……ああ、これが、女の子の、おまんこ……)
サヤが腰を前に突き出すと、黒々とした陰毛の中で、縦に割れたピンク色の肉の貝がシュンタの顔の前に突きつけられた。
(うっ……)
想像していたよりもグロテスクなそれの見た目と臭気に、シュンタは吐き気を催した。
とてもではないが、舐めろと言われても素直に応じることはできなかった。
「『お仕置き』」
「あ、ああああああ、ああああ!!」
シュンタがもたついているのを見たサヤがたった一言そう言うと、全身の震えが止まらなくなった。
(な、舐めなきゃ……早くここを舐めないと、また、サヤ様に……鞭で……)
先程刻みつけられた恐怖。黒光りする鞭が風を裂く音。自分の体に到達した瞬間の破裂音と激痛。叫んでも、暴れても逃げられない絶望。単純作業のように与えられる、おぞましいほどの痛み。薄笑いを浮かべながら鞭を振るう、サヤ。
「いや、いやだ、いやだ……!」
歯をガタガタと鳴らしながら、シュンタは震える舌を口から出した。
そして、異臭がするサヤの排泄直後の股間へとその舌先を近づけていく。
ネチャ……ヌチャ、ニチャ、ヌチュッ……
粘膜と粘膜が接触する音。恋人同士の舌が絡み合っても同じ音がする。
しかし今触れ合っているのは……
「あうう、ううう……」
ヌチャ、ヌチュ……
奴隷の舌と、女王様の女性器。
シュンタは涙を流しながら、 サヤの性器についた尿の飛沫を舐めとっていた。
(ううう、しょっぱいし、生臭い……)
そこは、シュンタがこれまで口にした物の中で最も汚く、屈辱的な味だった。
「よくできました。あなたたちオス奴隷の舌は私たち女子生徒の股を拭く為にあるのよ。よく覚えておきなさい」
「……ふぁい……わかり、まひた……」
シュンタはサヤの女性器の尿と恥垢の刺激的な味によって痺れる舌で、返事をした。
「最初だからみっちり指導してあげる。まずは今やってるみたいに表面を舐める。そして次は唇をすぼめる」
「こ、こうですか……?」
シュンタは自身の唇を突き出し、ひょっとこのような情けない顔をサヤに見せた。
「そう。そして口を尿道口に当てて、吸うの」
(にょ、にょうどうこう……?)
シュンタには、そう言われてもそれがどこなのか皆目わからなかった。
とりあえず、目の前にある肉の貝の中の穴の一つに唇を押し当てた。
「違う。そこは膣口」
ビシィン!!
「うぎぃ!!!」
シュンタの背中に鋭い痛みが走った。シュンタが顔を上にあげると、サヤが短い乗馬鞭を持っている。
よく見ると、トイレの壁には鞭をかけるフックがあった。そこから取ったのだろう。
「尿道口はその上。しっかりと吸い付きなさい。膣口には……後々嫌というほど舌を挿れさせてあげるから」
(……?)
シュンタにはよくわからなかったが、とりあえずサヤの言う穴に唇を押し当てた。
そして
チュウウウウ……
尿道口に口を付け、吸った。サヤの鞭に怯えながら。
「んぐっ……!」
その瞬間、シュンタの口の中に嫌な味の温かい液体が流れ込んだ。サヤの尿道に残っていた小便である。
「うぷッ……!」
気持ち悪い。今すぐこの便器に吐き出したい。そのことを伝えようと、シュンタは左手は口に当て、右手で便器を指差した。
しかし、それをサヤが許すはずがなかった。
「飲みなさい」
(そんな……!)
少量とはいえそれは人間の尿。生理的な不快感を伴い、飲み込むのは強い抵抗がある。
だが、サヤの顔はそれを許すような雰囲気ではなかった。
ゴク……!
「お、オエ……」
飲んでしまった。サヤの女性器から舐め取った、尿道から吸い取った小便を。
「そうそう。奉仕の時に口に入ったものは全てゴックン。基本中の基本だから、徹底しなさい」
サヤは「最後に全体を舐めて終わり」と何の気もなさげに言った。シュンタはその命令に従い、吐き気を抑えながら舌を這わせた。
「さて……」
サヤはパンツを履き、立ち上がった。
「次は夕食ね。私とあなたは食べる物が違うから。先にあなたから食べさせてあげる」
「私がトイレに行くときはあなたは必ず同行。それは絶対よ。覚えておきなさい」
「は、はい……」
シュンタには意味がわからなかった。「トイレ」と言えば、通常は必ず男女別。それなのに、なぜ同行させられるのか。
サヤがガチャリとトイレのドアを開け、手に持っているシュンタの首輪に繋がる鎖を引いた。
「何してるの。早く入りなさい」
「え……?」
シュンタは驚いた。なぜなら、てっきりドアの前で待機させられるのだと考えていたからだ。
「あ、あの……い、いいん、ですか……?」
シュンタは女性が便器に座って用を足す部屋の中に男である自分がいてもいいはずがないと考え、恐る恐る言った。
「クスッ。もしかして『男だから一緒に入れない』とか考えてる?」
「は、はい……だって、女の子が、男とトイレなんて……」
「この学園に『男』なんていない。ここにいるのは『女性』と『オス』のみ。あなた達は男じゃなくてオス。つまり動物と同じ。ペットのオス犬の前でトイレを恥ずかしがる女性がいるかしら?」
「そ、そんなぁ……」
この学園では自分は「男」とさえも呼ばれない。奴隷は動物や道具扱いで、「オス」。あまりにも横暴な考え方だとシュンタは感じた。
「ま、そんなことはどうでも良いわ。これからあなたがこれから三年間、私に行う奉仕の一つを教えるから。一度で覚えなさい」
シュンタはそう言われ、トイレの中に鎖で引き込まれた。
「は、はい……」
(なんだろう……トイレ掃除とかかな?)
シュンタが呑気な想像をしているのをよそに、サヤはトイレに入るとまず制服のスカートの中に手を入れ、パンツを下げた。
「う、うわ! そんな....!?」
シュンタは今日会ったばかりの女子が突然目の前で下着を脱いだのを見て声をあげた。
「何を驚いてるの。私はただトイレをするだけよ。あなたはそこに座りなさい」
サヤは平然とした顔でそう言って、洋式便器の前にある床を指でさした。
サヤはこれに関しては特に羞恥は無かった。三年前、黒椿学園に入学したばかりの中学一年生の時はこの行為に強い恥じらいを覚える自分もいた気がするが、中学の三年間で何度も繰り返してきた今は何とも思わない。
既に、目の前にオスを座らせて行うこれこそが自然な排泄のスタイルだと考えているところもある。
「よいしょ……」
サヤはスカートを捲り上げ、洋式便器に腰を下ろした。そして
ジョオオオオオオオオ……
「ふぅ……」
小便を、排泄した。ごくごく自然に、いつも通りに。
「あ、あ、あああぁぁぁ……」
目の前で、女性が排泄している。その異様な光景にシュンタは目を剥いた。思わず凝視してしまう。足首まで下げられたサヤのパンツを。水音を発しているサヤの股を。
(そうか。このオスの反応は当たり前か。外の世界で女性は個室で一人。終わったら『お股をトイレットペーパーで拭く』んだ。ふふ……私にはもう、そんなことはできないな。多分)
「ん……ふう……」
排泄を終えたサヤは小さな息を吐き、シュンタの方に向き直った。
「シュン。今からやるのはあなたたち奴隷の奉仕の一つ、『ビデ』よ」
「び、びで……?」
「そう。女性がオシッコをしたらお股を拭いて綺麗にしなきゃならないでしょう? あなたが主人である私のお股を綺麗にするのよ」
「あ、は、はい……」
サヤの命令に、シュンタに少し緊張が走った。そしてそれと同時に疑問も湧いた。
(要は、トイレットペーパーでサヤ様のお股を拭けってことか……あれ?)
「あ、あの、サヤ様……トイレット、ペーパーは……?」
「ああ、この学園には一つもないでしょうね。だって……」
サヤは左手でシュンタの髪を掴み、右手の親指と人差し指をシュンタの口の中に入れ、舌を摘んだ。
「私たちのトイレの後は、これで綺麗にするんだから」
「は、はひ……?」
パンツを脱いで下半身を露出させている排泄後のサヤに舌を掴まれたシュンタは、意味がわからないといった顔で情けなくサヤを見上げた。
「あなたたちオス奴隷は、私たち女性が排泄したらそこを舐め清めるのよ。それはこの学園では常識。ふふっ、これを覚えちゃうと普通のウォシュレットじゃ物足りないし、トイレットペーパーなんてもってのほか。やみつきになるのよね」
黒椿学園の卒業生には、卒業後に経営者や政治家となって活動している女性が多くいるが、いずれもが必ず「男性秘書」を従えていた。
その理由は必ずといっていいほど、この「排泄後の処理」のため。
黒椿学園の女生徒は中等部、高等部と6年間トイレ後にこの方法で秘部を綺麗にする。
その習慣が体に根付くので、卒業後もつい「男に舐めさせて拭く」以外の処理方法を避けてしまうのだ。
だから彼女たちはこの黒椿学園で身につけた調教技術を駆使して男を捕らえ、あるいは購入して調教する。排泄後に舐めさせるための男は何としても確保するのだ。
この方法には様々なメリットがあり、6年間でほぼ全ての女生徒が虜になってしまう。
「肌荒れしない、保湿できる、自動で動く、柔らかい、奴隷が直接見てするから丁寧に掃除できる。そして何より……ふふっ!」
サヤはシュンタの頭を掴み、シュンタの口を無理やり自分の性器にあてがった。
(惨めな奴隷の顔……ゾクゾクする……!)
サヤは生来のサディストではない。そしてサヤ同様、この学園に入学してくる女子のほとんどに元々Sの気質はなかった。
そもそも、まだ性にも目覚めていない中学1年生が「サディスト」であるわけもない。だから、黒椿学園は彼女達が将来オス奴隷を扱えるよう、彼女たちの心をSに目覚めさせる教育をしなければならない。
その方法として効果的なのが、この排泄後の舐め掃除。
人間の顔は、上目遣いをした際に最も弱々しく見える。
そして小便を舐め取らされる惨めさから、その目に涙でも溜まっていればさらに悲壮感が増す。
そのような情けない表情で見上げられながら、性感帯である性器を舐めさせる。
黒椿学園に入学したばかりの中学1年生の女生徒は、危険がないように、護身術を身につけるまでは主に幼い8〜11歳の奴隷で調教の練習をする。
サヤが初めて性器を舐めさせたのは8歳の奴隷。自分の前に跪いた奴隷が性器を舐めながら、涙目の上目遣いでサヤを見たその瞬間、サヤは背筋がゾワリと震えたのを覚えている。
そして何度か舐めさせた頃には「自分より弱い者を虐げる快感」に目覚めていた。
サヤ以外の女生徒達も、それまでは良家のお嬢様として育てられ、花を愛でるような優しい眼差しを持っていたが、何度もそうやって目の前に弱った獲物を用意され、可愛らしい奴隷に舐めさせた後には、弱者を甚振る肉食獣の目付きに変わっていた。
これが黒椿学園の教育方針。まずは「サディスト」として開花させる。弱者を踏みつけ、強者として振る舞うのが常であるように、彼女たちに教え込むのだ。
中等部で3年間教育を受け高等部に入学する頃には、優しく愛に溢れた「お嬢様」たちは、全員が厳しく奴隷に鞭を入れる「女王様」へと変貌していた。
「い、嫌です! こんなところ、おしっこの後なんて、汚いのに舐めるなんて……」
パァン!!
シュンタがそう言って抵抗の素振りを見せた瞬間、サヤの右手はシュンタの頬をビンタしていた。
「うぶっ!!」
自分の股を舐めない奴隷にビンタをする。それはサヤにとってあまりにも当たり前の行為で、殴られた痛みに驚いているシュンタとは対照的にサヤは冷静な表情だった。
「今のは警告。次に拒否したら『お仕置き』する。あなたがまた私の鞭の餌食になりたいのなら、どうぞ」
「あ、ああ、ああああああ……」
『お仕置き』という言葉を聞いただけで、シュンタの体の震えと涙が止まらなくなった。
(な、なんだ、これ……? ただ、『お仕置き』って言われただけなのに……?)
シュンタの頭には抵抗したい気持ちがあっても、体が全く言うことを聞かなかった。震えは止まらず、サヤの顔を情けない顔で見上げることしかできない。
「あ、あう、ああ、わかり、ました……」
シュンタはどうしても『お仕置き』だけは受けたくないと思い、諦めて舌を出し、サヤの股に顔を近づけた。
そしてシュンタが舐めようとしたのを見て、サヤは腰を前に突き出した。
(う……ああ、これが、女の子の、おまんこ……)
サヤが腰を前に突き出すと、黒々とした陰毛の中で、縦に割れたピンク色の肉の貝がシュンタの顔の前に突きつけられた。
(うっ……)
想像していたよりもグロテスクなそれの見た目と臭気に、シュンタは吐き気を催した。
とてもではないが、舐めろと言われても素直に応じることはできなかった。
「『お仕置き』」
「あ、ああああああ、ああああ!!」
シュンタがもたついているのを見たサヤがたった一言そう言うと、全身の震えが止まらなくなった。
(な、舐めなきゃ……早くここを舐めないと、また、サヤ様に……鞭で……)
先程刻みつけられた恐怖。黒光りする鞭が風を裂く音。自分の体に到達した瞬間の破裂音と激痛。叫んでも、暴れても逃げられない絶望。単純作業のように与えられる、おぞましいほどの痛み。薄笑いを浮かべながら鞭を振るう、サヤ。
「いや、いやだ、いやだ……!」
歯をガタガタと鳴らしながら、シュンタは震える舌を口から出した。
そして、異臭がするサヤの排泄直後の股間へとその舌先を近づけていく。
ネチャ……ヌチャ、ニチャ、ヌチュッ……
粘膜と粘膜が接触する音。恋人同士の舌が絡み合っても同じ音がする。
しかし今触れ合っているのは……
「あうう、ううう……」
ヌチャ、ヌチュ……
奴隷の舌と、女王様の女性器。
シュンタは涙を流しながら、 サヤの性器についた尿の飛沫を舐めとっていた。
(ううう、しょっぱいし、生臭い……)
そこは、シュンタがこれまで口にした物の中で最も汚く、屈辱的な味だった。
「よくできました。あなたたちオス奴隷の舌は私たち女子生徒の股を拭く為にあるのよ。よく覚えておきなさい」
「……ふぁい……わかり、まひた……」
シュンタはサヤの女性器の尿と恥垢の刺激的な味によって痺れる舌で、返事をした。
「最初だからみっちり指導してあげる。まずは今やってるみたいに表面を舐める。そして次は唇をすぼめる」
「こ、こうですか……?」
シュンタは自身の唇を突き出し、ひょっとこのような情けない顔をサヤに見せた。
「そう。そして口を尿道口に当てて、吸うの」
(にょ、にょうどうこう……?)
シュンタには、そう言われてもそれがどこなのか皆目わからなかった。
とりあえず、目の前にある肉の貝の中の穴の一つに唇を押し当てた。
「違う。そこは膣口」
ビシィン!!
「うぎぃ!!!」
シュンタの背中に鋭い痛みが走った。シュンタが顔を上にあげると、サヤが短い乗馬鞭を持っている。
よく見ると、トイレの壁には鞭をかけるフックがあった。そこから取ったのだろう。
「尿道口はその上。しっかりと吸い付きなさい。膣口には……後々嫌というほど舌を挿れさせてあげるから」
(……?)
シュンタにはよくわからなかったが、とりあえずサヤの言う穴に唇を押し当てた。
そして
チュウウウウ……
尿道口に口を付け、吸った。サヤの鞭に怯えながら。
「んぐっ……!」
その瞬間、シュンタの口の中に嫌な味の温かい液体が流れ込んだ。サヤの尿道に残っていた小便である。
「うぷッ……!」
気持ち悪い。今すぐこの便器に吐き出したい。そのことを伝えようと、シュンタは左手は口に当て、右手で便器を指差した。
しかし、それをサヤが許すはずがなかった。
「飲みなさい」
(そんな……!)
少量とはいえそれは人間の尿。生理的な不快感を伴い、飲み込むのは強い抵抗がある。
だが、サヤの顔はそれを許すような雰囲気ではなかった。
ゴク……!
「お、オエ……」
飲んでしまった。サヤの女性器から舐め取った、尿道から吸い取った小便を。
「そうそう。奉仕の時に口に入ったものは全てゴックン。基本中の基本だから、徹底しなさい」
サヤは「最後に全体を舐めて終わり」と何の気もなさげに言った。シュンタはその命令に従い、吐き気を抑えながら舌を這わせた。
「さて……」
サヤはパンツを履き、立ち上がった。
「次は夕食ね。私とあなたは食べる物が違うから。先にあなたから食べさせてあげる」
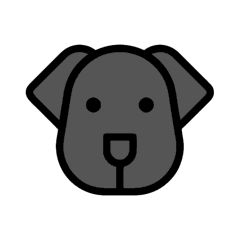
17
1715443302
Re: マツダカコ最新长篇大作《女王達の学舎》(4月3日更新鞭打 小便 舔阴)
有偿翻译要不
这个作者又开始更新了,有人知道怎么看到她以前的小说吗?